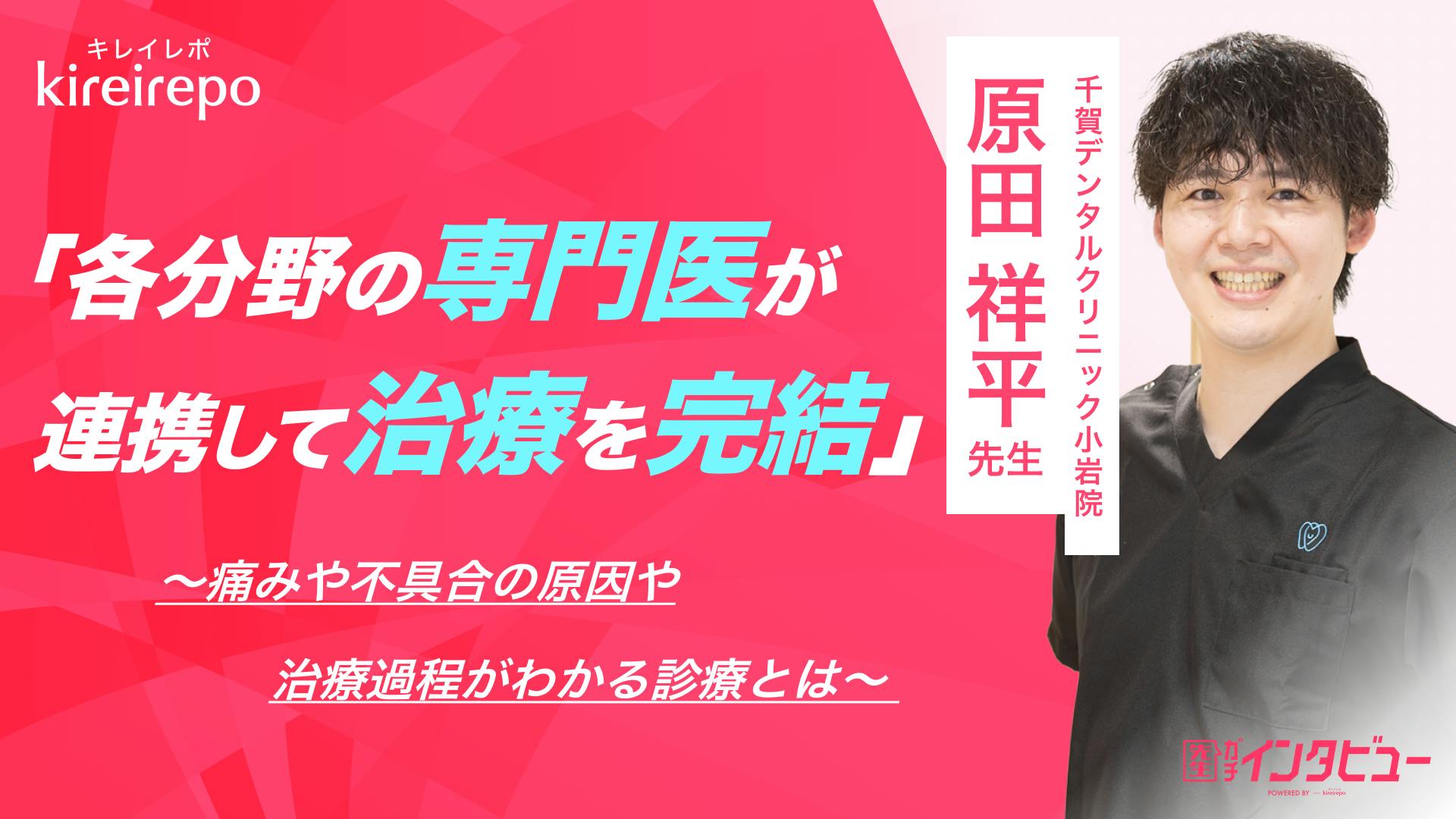「歯科医院は歯を治すだけの場所ではない」口元から全身の健康を向上・維持させる治療を提供|きみえ歯科 中村 喜美恵院長
今回取材させていただいた先生
インタビュアー


きみえ歯科の強みを教えてください。

お口の中だけでなく全身の健康を考えた上で、治療しています。
一般的に、歯科医院は虫歯や歯周病を治すだけの場所と思っておられる方が多いかと思います。しかし、体はすべて繋がっているので、口腔環境改善のためには全身の健康を考える必要があります。
口腔内の細菌は、全身に発症しうる100以上の病気に関係していると言われます。特に、糖尿病や心疾患、骨粗鬆症、低体重児出産・早産などが、歯周病と深く関係していることは、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
お口の中には800種を超える細菌が生息すると言われ、腸内と同じように善玉菌と悪玉菌が存在しているのですが、菌のバランスが取れていれば特に問題はありません。しかし、悪玉菌が増えると虫歯や歯周病へのリスクが大きくなるだけでなく、悪玉菌が全身に運ばれることで全身の病気のリスクも高くなってしまいます。
当院では、最初の診査の際に、口腔内の細菌を生きた状態で顕微鏡(位相差顕微鏡)で確認するところから治療を開始し、薬剤を使用せずに安全に口腔内の悪玉菌を除菌する方法を提供しております(善玉菌は除菌してはいけないため)。
また、全身の皮膚はひとつながりで、筋肉も連動して動いています。ボルトやナットでねじ止めされている箇所はどこにもありません。ですから、普段の癖や習慣が歯並びやかみ合わせ、口腔周囲の筋肉などに影響を与えるのです。もちろん、お顔の形や笑顔にも大いに関係してきます。
患者さんには5年、10年後も変わらず健康に過ごして頂きたいと願っておりますので、歯科医院ですが筋肉のつき方や姿勢など全身を診て治療の判断をしています。

お口の健康が全身の健康に繋がるんですね。では、お口のケアはいつから始めるべきでしょうか?

乳幼児のときからお口の健康を意識し、お口のケアに関心を持ち続けていただきたいです。
乳幼児のときから意識していただきたいですね。例えば、お子様の場合、乳歯だけでなく乳歯の下にある永久歯も見ます。
乳歯にかかる力は、その後生えてくる永久歯にも影響します。乳歯にかかる力が良くないと、その下にある永久歯は、骨の中で傾いたり歯根がうまく育たないななどの症状がみられ、それにより永久歯の歯並びや噛み合わせが悪くなってしまいます。
親御さんの中には、「乳歯は抜けるから」とそこまで気にされない方も多いのですが、乳歯にはいい働きをしてから抜けて欲しいですね。何と言っても、お子様が成長した後のお口の健康に関わるのです。
現代は人生100年と言われています。年齢を重ねていくと、長年にわたる歯並びや噛み合わせの影響の蓄積や、良くない習慣や習癖の継続により、顎の関節のずれや痛み、頭痛や肩こりといった体の不調が出てくる方が増えてきます。また、歯のすり減りやひび割れ、更に折れてしまうなどの問題も起こりやすくなってきます。
私たちは自分の歯を100年もたせることを考えなければいけない時代に生きているのです。年齢を重ねてくると全身に影響が出ることを意識して、若い時から歯に関心を持っていただきたいです。
正しい姿勢が「健康の基本」

虫歯や歯周病の予防で意識するべきことは何ですか?

正しい姿勢できちんと咀嚼をしてしっかりと唾液を出すことが重要です。
唾液には抗菌作用や毒素・異物を排除しようとする働き、むし歯を防ぐ働きがあります。
また、咀嚼により唾液と食物をお口の中でしっかり混ぜ合わせることで、唾液の中の消化酵素が良く働き胃腸の働きも助けますので、身体にも大変良い影響を与えます。更に、唾液には美肌ホルモンも含まれていますので、美容にも効果があります。
しっかりと唾液を出すためには良く咀嚼できていることが必要不可欠ですが、食事中の姿勢が悪いと上手く噛むことができないので、口腔環境を整え、正しく咀嚼することが大切であることを覚えていていただきたいですね。

姿勢が悪いと、どのようなことが起こりますか?

舌は下顎の骨と筋肉でつながっていますし、また、舌は胸や背中とも筋肉でつながっています。ですから、姿勢が悪くなると、舌や下顎の動きが悪くなります。そして、噛み方や噛む位置、飲み込み方に良くない影響を及ぼします。
しっかり噛んでいるつもりでも、姿勢が悪いと実はあまり噛めていないことが多いのです。
ここで、姿勢と咀嚼の関連性を検証した「おむすび咀嚼実験」をご紹介します。これは、被験者の人に (1) 、(2)、(3)の姿勢でおにぎりを食べてもらい、咀嚼回数を比べた実験です。
(1) 正座
(2) 足を地面につけて椅子に座った状態
(3) 足が宙にぶらぶらした状態で座った状態
結果は (1) > (2) > (3)の順で、 (1) の正座をしている人の咀嚼回数が最も多くなりました。足元が安定する姿勢で咀嚼すると、それだけで自然と咀嚼回数が増えていきます。
この実験結果から、しっかり咀嚼するためには、姿勢がとても重要であることがわかっていただけると思います。
現代の生活スタイルでは、ほとんどの方は正座をすることはないと思いますので、最低限(2)の「足を地面につけて椅子に座った状態」を意識して、食事をして頂きたいですね。

姿勢や習慣の矯正指導で工夫されていることはありますか?

実践を継続してもらえるように、伝え方を患者さんによって変える意識をしています。
例えば、「正面を向いて奥歯で噛んでください」とただ指導するのではなく、「下を向いて前の方の歯で噛むと、シワやたるみの原因になるので、奥の大臼歯でしっかり噛んでください。」とお伝えすると患者さんが興味を持たれ、実践しようと思って下さいます。
患者さん自身がご自分のことを理解されたうえで実践されることが重要です。私たちは、興味を持ってもらえるように工夫しつつ、押し付けにならないようにお伝えすることを意識しています。
お子様の頃から来院してもらいたい

先生が治療の際に気をつけていることを教えてください

麻酔を打つ際に痛みを感じないよう細心の注意を払っています。
まずは、麻酔を打つ際に痛みをできるだけ感じないように努力をしています。歯科医師になる前に歯科治療を受けて、「歯医者さんで打たれる麻酔ってなぜこんなに痛いのだろう?」と思っておりましたので、開業当初から痛くないように細心の注意を払ってきました。
表面麻酔の使用や麻酔針の細さ、麻酔薬の温度に注意するのはもちろんのこと、刺入時の痛みをできるだけ感じないような工夫をしています。

最後に、来院を考えている方へメッセージをお願いします

子供の歯からずっと支えていきたく、できるだけ早くからみなさんに出会いたいです。
年齢関係なく沢山の方の歯を診ていきたいのですが、特にお子様の歯はずっと管理していきたいと思っています。乳歯から永久歯への生え変わり、その先の歯並びや筋肉の動かし方のことも考えると、早くからご来院いただけたら嬉しいです。